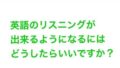「新古今和歌集」の中の後鳥羽上皇の一首
『見渡せば山もと霞むみなせ川夕べは秋と何思ひけん』
上皇は自分の愛した水無瀬の離宮のほとりの川で、春の夕暮れ、霞に包まれた風景を見て、
これまで夕方の景色は秋に限ると思いこんでいたのはどうしてだろうと、わが心をいぶかしんでいる、といった、風情の歌です
この「夕べは秋」とは、
「清少納言が、秋は夕暮れと言いだれもが、そして自分も そう思いこんで来たけれども」
が挿入されて正しい理解となり、当時の文化人には「夕べは秋」と言えば、
「ああ、『枕草子』のあそこを言っているのだな」
と思うくらい「枕草子」の自然観が浸透していたのです
そして後鳥羽上皇 鎌倉時代からおよそ500年弱、元禄文化が花開こうとしていたころ世界最小の文学
「17文字の芸術」
を極める俳諧師がこの世に生を享けます。
(「俳諧」や「発句」の意味がわからない
場合はググってもらうとしてwww)

『古池や蛙飛びこむ水の音』
この発句は「古池」や「蛙」が美しいと言ってるわけではなく、「水の音」が妙音だと主張しているのでもありません。
ただ古い池に蛙が飛びこんだ その一瞬に起きた小さな音によって逆に辺りの静けさが強調された深い静寂の世界に新しい美を見出したもので、そこには何の実体もなく、あるのはただの状況だけで、すなわち『状況の美』が凝縮された作品です。
と、これが『今』においての定説です
この句は1686年の春、芭蕉庵での蛙の句合せに出された句で
弟子の各務支考の著書『葛の松原』によれば、
芭蕉はまず「蛙飛び込む水の音」をつくり
弟子の宝井其角が、上五は「山吹や」がいいのではとすすめたのですが
芭蕉は「古池や」にしたーーーといってます
山吹か古池かで議論があったとも書いてあります。
其角が山吹をすすめたのは
「かはづ鳴くゐでの山吹散りにけり花のさかりにあはましものを 」
などの古今集の歌などを思い浮かべたから
であり、山吹といえば蛙の声、蛙の声といえば山吹をもってくる和歌の伝統に対し『声』ではなく『飛びこむ音』をぶつけ、山吹には蛙の声、という
古臭い因襲への批判を考えていたのです
(当時其角は和歌の因襲を批判していた)
それに対して芭蕉が古池をもってきたのは芭蕉には因襲へのあらわな批判も
ひとつの因襲と映っていたのかも
しれません
芭蕉の古池の句は当時の俳諧という和歌の因襲を意識した「場」に深く根ざしたものであったのですが
現在では時間とともにその「場」が失われ
この句が本来もっていた和歌や当時の俳諧に対する創造的批判という意味が見えなくなり
残ったのは、
古池にカエルが飛びこんで水の音がした
ただこれだけとなっています
(俳句の宇宙他多数より引用)