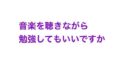ある日
私の友人は小学生の子供と教材選びに出かけたそうです
数ある教材の中から最終的に3つほどに絞り、
悩んだ末に一番ハイレベルなものを買って与えたそうです
友人の子はとても優秀でしたので、悩んだ末この教材を選択したのだと思います
しかしこの教材に取り組んだ子供は出来なすぎて凹んだそうです
このように教材選びで迷った時、より難しいほうを選んでしまう生徒や親御さんが多いようです
「難しい問題を解いていれば基本問題は簡単に解けるようになるはず」
そういった理屈のようですが、ほとんどの生徒は難しい問題を解けるようになる前に、挫折することになるので注意が必要です
こと教材選びに関しては、「どちらか迷ったらラクそうなほう」を選ぶのが賢明かと思います
たとえば高校数学で、青チャートか黄チャートかで迷ったら、黄チャートを選ぶべきです。いや、偏差値50未満の生徒(安房高生の8割がこの仲間に入ります)なら白チャートでも十分です。
安房高では上位半数に数学の副教材として青チャートを持たせていますが、実際に青チャートを全うできる生徒は数学が得意な10人ほどです
青チャートの解説は基礎的な部分や基本公式や途中式など理解している人達が利用する教材なので解答解説にその部分は記載されてません
したがって青チャートを配られた上位120人のうち残り110人の生徒たちにとって青チャートは解説が粗くてチンプンカンプンなはずです
では、ここでチャート式参考書の色と内容について簡単に説明しておきます
チャート式参考書は主に「白チャート」、「黄チャート」、「青チャート」と3冊あります(主にです)
白チャート
学校の授業や定期テストのサポートのため解説も丁寧に書かれています
(解説は丁寧に書かれていますが安房高の下位半数の生徒には、白チャートでも難しすぎて消化しきれない難易度の教材です)
黄チャート
定期テストは80点くらい取れているけど模試などの問題に対応したいという人に向いています
この参考書で共通テスト基礎基本レベルまで対応できると思ってください
(安房高で数学定期テスト80点取れる生徒は上位30人ほどしかいませんが、これらの生徒たちには黄チャートが向いています)
青チャート
定期テストレベルは問題なく、さらに応用問題や模試で高得点を取りたいという人に向いています(安房高の上位10人ほどの生徒に向いています)
文理問わず難関大学まで対応できますので逆にいうとオーバーワークになってしまわないように注意が必要です
なんとなく青チャートを取るという人がいますけれども、皆さんのレベルに合っていなければ理解はもちろん、進まないし、消化しきれません
実際にうちの塾生を例に挙げますと、うちの塾生はとても優秀ですが教科の中ではとくに数学が苦手で定期テスト85点くらいしかとってこれません。このレベルの生徒が「青チャートは難しくて無理」と言って青チャートは本棚の飾りになってます
.
.
.
安房高の数学を例に出しましたが、要するに「ラクそうなほう」を選んだとしても、「簡単過ぎる」なんてことは絶対にないので心配いりません
子供たちにはよく話すんですが、テストが難しくなればなるほど基礎力の差が出るものです
私が言っていいる「基礎力」とは簡単な問題が解けるという意味ではありません
1問1問なぜこの答えになるのか答えられる力ということです
小学生、中学生の『はやさの問題』で「ハジキ(みはじ)の公式」にただ数字を当てはめて解いている子は、仮に問題に正解していたとしても「基礎力はない」ということです
どうでしょう
これでも「自分に基礎力がある」と自信を持って言える人ってどれだけいるでしょうか?
「基本は出来るけど応用はできない」のではなく
「基礎力がないから応用もできない」のです
子供たちや親御さんには、このことを理解して欲しいと思っています
.
.
友達が何やら難しそうな教材をやっているのを見て、
自分のやっている教材に不安を覚えたことはありませんか
「自分はこれで大丈夫なんだろうか?」
「もっと難しいのをやったほうがいいんじゃないかな?」
私も学生の頃はいろいろと目移りしたこともあるので、その気持ちはよくわかります
けどその友達は、本当にそれを全うできているんでしょうか?
心配いりません。
少なくとも私の知る限り、よほど優秀な生徒でない限り、それを使いこなせている生徒は皆無です
それどころか、ただの置物になっているケースがほとんどです
持っているだけで賢くなれるなら、誰でも東大に入れますよねwww
難しそうな問題集で結局挫折するくらいなら、「ラクそうなほう」を全うしたほうが何倍も力が付きます
難問に心を乱されるのではなく、基本を徹底的に確認して基礎力を養いましょう
教材選びで絶対にやってはいけないのは「背伸び」です
自分が解いた問題、なぜその答えになるのか、全て説明できますか?
.
.