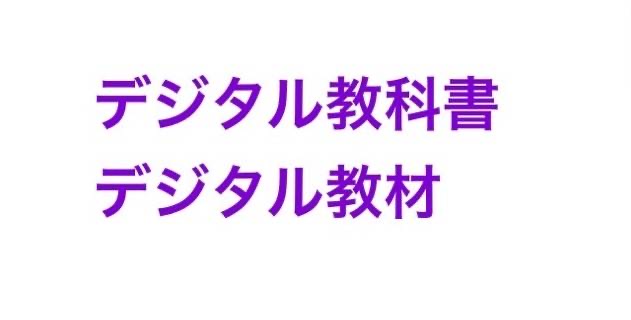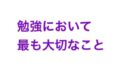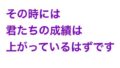長いこと教育先進国と言われ、
早くからデジタル化を進めてきたフィンランドではノートPC無料配布も、学習成果は低下し、
今、逆に「脱デジタル化」の動きが加速しています
タブレットやノートPCを使った学習から、
今は紙と鉛筆を使った学習に逆戻りしているのです
原因は世界トップクラスを誇ってきた子供たちの学力がデジタル化を機に低下してきたからだそうです
.
.
日本でも遅ればせながら「デジタル教科書」を正式な教科書として認める方針を文科省が示しました
当面はどちらを使うかは各教育委員会が決める(紙との併用を含めた)選択制の導入だそうです
この文科省の方針を『拙速』として真っ向から反対しているのが東京大学大学院教授で言語脳科学者の酒井邦嘉氏です
彼の研究によると「紙とペン」の方が「タブレットとキーボード」よりも記憶の定着率が高いという結果が出ているそうです
同様に小中学校の校長の多くもデジタル教科書への全面移行には強い懸念を示しているそうです
.
.
方や欧州諸国では教科書を含む教育現場のデジタル化を見直す動きが加速しています
IT先進国のスウェーデンでは国際調査で子供の学力が落ち込み学習への悪影響があるとして「脱デジタル」、「紙と鉛筆を使った従来のアナログ方式での授業に戻す」方針が示され政府は紙の教科書の再普及に巨額の予算を投じていますし
ノーベル生理学・医学賞の選考期間でもあるカロリンスカ研究所は「印刷された教科書や教師の専門知識を通じた知識の習得に重点を置くべきだ」と訴えてもいます
また、低年齢の子どもたちでは、手で文字を書く練習が不足することで運動能力、脳の活性化、言語発達などが低下することも懸念されるそうです
また、慶應大学 教育方法学 藤本和久教授も「海外の事例を参考に、デジタル教科書の有効性や課題について議論を十分に尽くした上で、使い方を考えるべきだ」と指摘しています
デジタル化が進むことによって、
逆に手書きの大切さが見直されてきているということなのかもしれませんね
うちの塾生の中にも「東進オンライン学校」、「スマイルゼミ」、「進研ゼミ」などのデジタル教材を経験したのち、(思ったほどの成果が得られなかった)という理由で入塾してくる子がいます
私は、これらの教材がダメだと言ってるわけではありません。
これらを与えさえすればほっといても子どもたちは勉強してくれて学力をつけてくれると思い込んでいる大人の方の責任が大きいのではないかと考えています(デジタル教材って安価ですもんね気持ちは分かります)
けど小中学生のほとんどは、まだまだ子供です、
自分で自分の勉強の管理は出来ない子がほとんどなのです
このことを大人は理解する必要があるのではないでしょうか?
先日、塾専用教材の営業の方が来られて話をしましたが、
彼曰く「塾の良いところは先生の熱量で生徒を引っ張っていける」ところだそうです
私は(あゝ、なるほど、的を得たこと言うなあ)と思いました
本当の「効率」を得るためには
やはりある程度の「非効率」を経る必要はあるような気がします
.
.