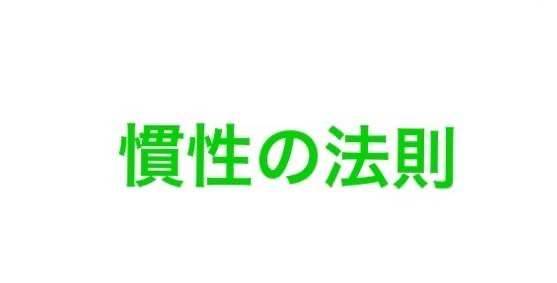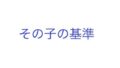運動している物体はいつまでも同じ運動を続けようとし、
静止している物体はいつまでも静止し続けようとする
学生時代、理科が苦手だったという方でも、その言葉くらいは頭の片隅にあるのではないでしょうか
これって人間の脳にも同じことが言えますよね
勉強を習慣にしている人はいつまでもその勉強を続けようとし、普段勉強をしていない人はいつまでも勉強しないように脳が働く
脳は変化を著しく嫌う特徴を持っているので、やっている人はやらないことを嫌い、やっていない人はやることを嫌う。そんなところでしょうか。(私たちが「お金持ちになりたい」と思いながらも、そのための行動を起こさないのもこのためのようで)
私たちはよく子供たちに対して、「やる気がある」とか「やる気がない」といった言い方をしてしまいます
「やる気があれば出来る」
「やる気がないから出来ない」
といったように
でも、脳の専門家の方によると、この考え方は間違いで、
「やるからやる気が出る」
「やらないからやる気が出ない」
というのが本当だそうです
つまり、やる気のあるなしが先ではなく、やるかやらないかが先だということですね
確かに過去の教え子の中にも、やる気は人一倍あるのに全くやらない子がいました
一方でやる気はいまいちでも、習慣(惰性?)で最後までやり続けられた子もいました
勉強は、やる気よりも習慣が大事ということですね
そしてこの習慣は、早ければ早いほど身につけやすいのは言うまでもありません
といっても、早いうちから結果にこだわり過ぎた勉強は、勉強嫌いにさせてしまう危険もあります
小学校のうちは「出来るか出来ないか」よりも「勉強習慣をつける」ことを第一の目的にされるのがよろしいのではないかと思います
小学校でしっかり勉強の習慣をつけた子は、中学校以降の勉強も「慣性の法則」で何とか乗り切れることが多いです
.
.
やはり人間の脳は「慣性の法則」に支配されているのかもしれません