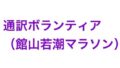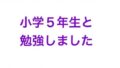わたしの街には那古寺という那古山の山腹に建てられた寺があります。
那古山を、山頂に向かって登ると那古寺がありますが、さらに上へ登ると、海を目下に潮の音を聞くことが出来るということから、潮音台と名付けられた広場に出ることができます。
そこには、
「あらざらむ〜」の歌が書かれた東屋と、和泉式部と娘の小式部内侍の供養塚があります。

〈後拾遺和歌集・763〉
あらざらむ この世のほかの思ひ出に いまひとたびの あふこともなが
口語訳
私はもう長く生きられそうもありません。
来世での思い出になるようにせめてもう一度あなたにお逢いしたいものです。
この歌は和泉式部が病に倒れ、死期が近いと悟ったときに詠んだ歌です。
詩書には、「心地例ならずはべりけるころ、人のもとにつかはしける」とあります。
歌の通り、年老いて、病床に臥しているためもう長くは生きていられないと悟った時、心残りを歌にして愛しい人のもとへ送ったということだと思います。
あの世へ持っていく思い出に、もう一度だけあなたに逢いたいというストレートな感情を装飾なくシンプルに詠んだという印象を受けます。
掛詞や、枕詞などの難しい技法が使われていないため、シンプルならではのひたむきさや必死さが感じられます。
さらに「あらざらむ」から始まるこの歌のインパクトです。
生きてはいないだろう、から始まることで、死期が迫っている女性が絶え絶えになりながら、またあなたに逢いたいと心から叫んでいる情景が思い浮かびます。
ひたむきさ、必死さを超えた狂おしいほどの情をこの部分からかんじます。
和泉式部は恋多き女性で、恋の達人でした。
最初の夫である橘道貞から為尊親王、為尊親王の弟である敦道親王、藤原保昌と一生の間で4人もの男性と生活したことはかのじょがそれだけ魅力的な女性だったということの表れであると言えます。
しかし、為尊親王との恋愛の際に和泉式部の父である越前守大江雅致には勘当され、為尊親王、敦道親王とは死別。
当時の権力者であった藤原道長には「浮かれ女」といわれ、娘には先立たれるなど華やかな恋の裏には苦労もありました。
この歌は先立った娘に当てたのではないかという意見もありますが、詞書にある、「人」はこの4人の中では誰を指しているのでしょうか。
わたしは敦道親王ではないかと考えます。
最初の夫、橘道貞は陸奥守に引き立てられたことをきっかけに新しい妻を引き連れて京から出て行ってしまい、そのために和泉式部とは離縁していきます。
未練があったにしろ、次の恋に進んでいるという点から道貞ではないと考えます。
二番目の夫、為尊親王は情熱的な求婚をした末に和泉式部とむすばれますが、結ばれてから一年ほどで崩御してしまいました。
結ばれる過程で親に勘当されていた和泉式部は彼が亡くなった後、何か月もぼんやりと過ごしていました。
そこにあらわれたのが三番目の夫、敦道親王です。
敦道親王は長く喪に服す和泉式部のもとに為尊親王に仕えていた子どもを遣わせ、橘の枝を送ったことから周りの反対も気にせず結ばれていきます。
しかし、幸せだったのも束の間、敦道親王も兄と同じくわかくして崩御してしまいます。
四番目の夫、藤原保昌は和泉式部と歳が離れていました。
そんなこともあり、結婚生活はあまりうまくいっていませんでした。
彼とともに田舎に下った和泉式部でしたが京での暮らしを恋しがり、夫を田舎に残したまま単身で京に帰っていきます。
そしてのちに、二人は別れてしまいます。
私が敦道親王だと考えた理由は和泉式部の落胆している様にあります。
いろいろなことが思い出されるようで、彼が崩御してからの恋慕の思いを120首余りもの歌に残しています。
「片敷きの袖は鏡とこほれども影に似たるものだにぞなき」
(片方に敷いて寝ている私の袖は涙に濡れて、濡れた袖が凍り付いて氷となっている。氷なら鏡のようにあの人の姿が映ってよいものを何も映らない)
や、
「黒髪の乱れも知らず打伏せば先ず掻き遣りし人ぞ恋しき」
(黒髪が乱れているのも構うことなく伏していると、何よりも真っ先に、私の髪をかき上げてくれたあの人の事が思い出される)
と悲痛ともいえる歌を多く読みました。
さらに、出家し仏の道へ進もうとまで考えていました。
「斯くばかり憂きを忍びて長らへばこれに増さりて物もこそ思へ」
(このように悲しさをこらえて長生きしても苦しいばかりだ。いっそ世を捨て出家したい)
や、
「捨て果てんと思ふさへこそ悲しけれ君になれにし我身と思へば」
(身を捨て出家しようと思うと、いよいよ悲しみがこみ上げるのです。長いことあなたとなじんできたこの体だと思うと)
と出家の決意をしても彼との思い出が和泉式部を離してくれません。
これらのことから敦道親王へ向けた歌だったのではないかと考えられます。
晩年の様子が残されていない和泉式部ですが、尼となり誠心院と名乗ったと言われています。
「あらざらむ〜」の歌は、晩年の和泉式部が波乱万丈の生涯を思い出しながら詠んだのでしょう。
恋多き女性、和泉式部が最後に自分の気持ちを素直に詠んだ歌、情熱的な女性の中にある儚さと素直さが感じられる歌ではないでしょか。
.
.
.